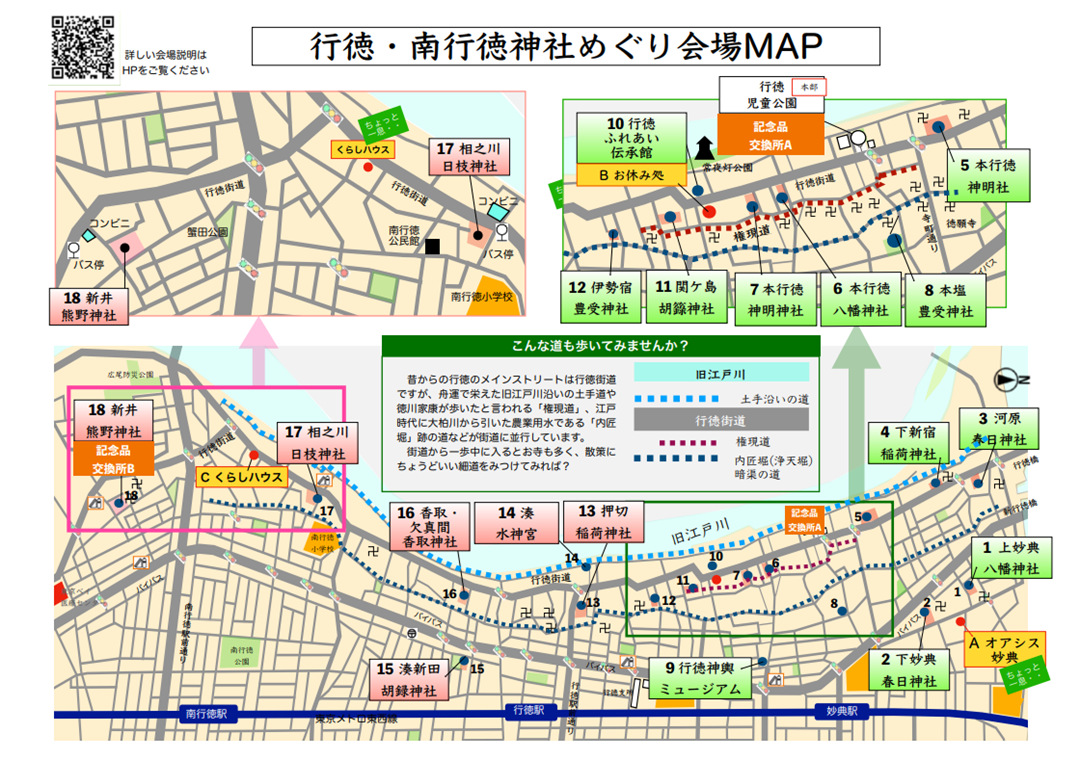コロナ禍真っ只中の前回2022年において唯一実施された四ヶ村例大祭の本祭。
三密(今となっては懐かしさすらある)が避けられない状況ながらも、最大限の感染予防対策をとりつつ神輿渡御が行われたものでした。
担ぎ手の方々もマスク着用で臨んでいたのが思い出されます。
それからあっという間の3年。
お隣の相之川でも神輿渡御が6年ぶりに開催され、以前のような同日で江戸前担ぎと行徳もみを見ることのできる光景が復活いたしました。
神輿のまちに賑わいが戻ってきたことを喜びつつ、ふたつの祭りを行ったり来たりの同時レポ。
四ヶ村例大祭はこの記事、相之川の大祭はこちらの記事にまとめました。

■香取から湊へ引き継がれる宮神輿
2025年10月12日の日曜日。
懸念されていた台風接近が回避され、好天に恵まれた一日となりました。
7月の胡録神社祭礼と同じような天候に、地神様のご加護を感じざるを得ませんね。
香取神社の宮神輿は朝から4つの町内を巡行しています。
11時の時点では既に欠真間から香取へ引き継がれていました。
時折歩みを止めて、行徳担ぎの華「もみ」を行います。
最初に地面すれすれまで神輿を下げる「地すり」。

続いて片手で支えて神輿を高く差し上げる「さし」。

最後に神輿を空中に放り上げて受け止める「ほうりうけ」。

宮神輿の渡御を終えた欠真間では、町会神輿が町内を練り歩きました。
欠真間カラーのピンク色飾り紐をまとった町会神輿。
担ぎ手が身につける帯やタオルもピンクです。
なかには髪色をピンクに染めている担ぎ手も。

源心寺前を通過し行徳街道を進む宮神輿。
正午過ぎには香取神社の前に到達していました。
それにしても建て替えられたばかりの香取交番は、ずいぶんコンパクトになってしまいましたね。

宮入りのときを前にひっそりとした香取神社境内。
縁日の露店代わりにキッチンカーが出店していました。

香取の担ぎ手が宮神輿を担ぐのはここまで。
3つ目の町である湊新田へ引き継がれます。
が、そう簡単に受け渡しするわけがなく。

行徳の祭りの風物詩、神輿とバスとのすれ違い。
やって来たのはグループ内再編により今年4月誕生した京成バスウエストの路線バス車両。
トリコロールカラーの車体もいずれ見慣れたものになるのでしょうね。

かれこれ30分近く経ったでしょうか。
ついに湊新田へと引き渡された宮神輿。
紫色の帯を締めた担ぎ手たちによる初めてのもみです。
この後しばらく湊新田を巡行し、最後の町内である湊に引き継ぐこととなります。

■宮神輿は湊新田から湊へ
午後いったん離脱し、14時半過ぎに再び行徳街道へ。
途中の香取では町会神輿が香取内を巡り歩いていました。

香取神社の宮神輿は台輪寸法三尺五寸、行徳神輿の中では大きめです。
製作者や製作年代は不明ですが、損傷の激しさに大正時代から65年もの間担がれることがなかったというのに驚かされます。
修復された現在の姿をみると全く想像つきませんね。

宮神輿の湊新田巡行もあとわずか。
湊新田の担ぎ手たちが見事なさしを披露しています。

湊新田と湊の境界で引き渡すことになりますが、当然のごとく一悶着あります。
白い帯を身につけた湊の担ぎ手たちと対面する中もみ続ける湊新田の担ぎ手たち。

ほうりうけが終わるともれなく引き渡しの攻防が始まります。
緊迫感に包まれながら盛り上がる瞬間です。

引き渡しが阻止された宮神輿は、進行方向を変えて逆戻り。

攻防の直後はもむのがお約束。
引き渡しが阻止できた場合は喜びの「もみ」ですね。

宮神輿が湊に引き継がれたのは15時少し前。
ここから神輿渡御の最終ルートが始まります。

さてここからは最後の町、湊の渡御が始まります。
押切との境界付近で揃ってもみを披露する宮神輿と町会神輿。

湊の町会神輿は前々回の2019年より女神輿として担がれるようになりました。
白装束に身を纏い、地すり→さし→ほうりうけの所作を行うのは男性と変わりません。
長らく女人禁制だった行徳担ぎも時代の流れによる変化が徐々に。
女性の担ぎ手による力強いもみに勇気づけられます。

湊を飛び出し押切の町内へ入る宮神輿と湊の町会神輿。
押切稲荷神社を通り過ぎ、行徳駅方面へと向かっていくのはいいのですが、どこまで行くつもりでしょうか。

バイパスひとつ手前の交差点で曲がるよう音頭取りに促される2基の神輿。
その先に進もうとする担ぎ手たちとのひと悶着がここでも発生しています。

宮神輿が向きを変えた後、男女混合で担ぎ始めた町会神輿も続くかと思いきや、宮神輿よりも粘る粘る!
女性の担ぎ手もいる小さな神輿とはいえおとなしいわけではなく、神輿のまち行徳のスピリットは世代や性別を超えて脈々と受け継がれているのですね。

■各町を巡る町会神輿の渡御
宮神輿の渡御と別れて相之川方面へ向かっていると、香取一丁目の町会神輿に再び遭遇しました。
町会神輿とはいえ宮神輿と遜色ない大きさ。
台輪寸法が同じうえに姿かたちも似ているため見分けつきにくいですが、黒地に香取と大きく書かれた駒札が町会神輿、シンプルに香取神社と書かれた駒札が宮神輿になります。

16時10分、香取の町会神輿が香取神社に宮入りしました。
この後行われる宮神輿の宮入りとは違い、あっさりとした宮入りです。

相之川の神輿渡御を見に日枝神社へ向かっていた途中、欠真間の町会神輿が出発するところに立ち会うことができました。
ちょうど日枝神社前の交差点が相之川と欠真間の境界線。
道一本隔てて担ぎ方や衣装が大幅に変わるのが大変興味深いです。

4つの町を渡り歩いた宮神輿は白丁に引き渡され、担ぎ手たちにより香取神社への宮入りが行われるのが最大のクライマックス。
今回は相之川の宮入りを見届けたため、こちらは見ることができず残念(身体がふたつあればいいのに)。
激しい宮入りの模様は前回2022年のレポをご覧ください。
3年ぶりの四ヶ村例大祭神輿渡御お疲れ様でした!
■神輿のまち行徳の祭りよ永遠に
神輿のまち行徳で複数の町会により宮神輿を引き継ぐ渡御はここ四ヶ村と五ヶ町のみ。
神輿を引き渡すときの町同士の激しい攻防は、神事における人間模様が感じられるひとこまです。
白装束と行徳もみの基本は崩さず、激しいながらも粛々と渡り歩く神輿渡御は、いつ見ても行徳らしさを実感できる光景です。
次回開催は3年後の2028(令和10)年、もう令和も2桁ですか。
コロナ禍を乗り越え令和や次の時代になっても、行徳神輿と祭りの伝統が続きますように。
▼四ヶ村例大祭(相之川日枝神社大祭)レポートはこちら :2025年(四ヶ村) 2025年(相之川) 2022年(四ヶ村のみ) 2019年(四ヶ村・相之川) 2016年(四ヶ村・相之川) 2013年(四ヶ村・相之川) 2010年(四ヶ村・相之川) 2007年(四ヶ村・相之川)